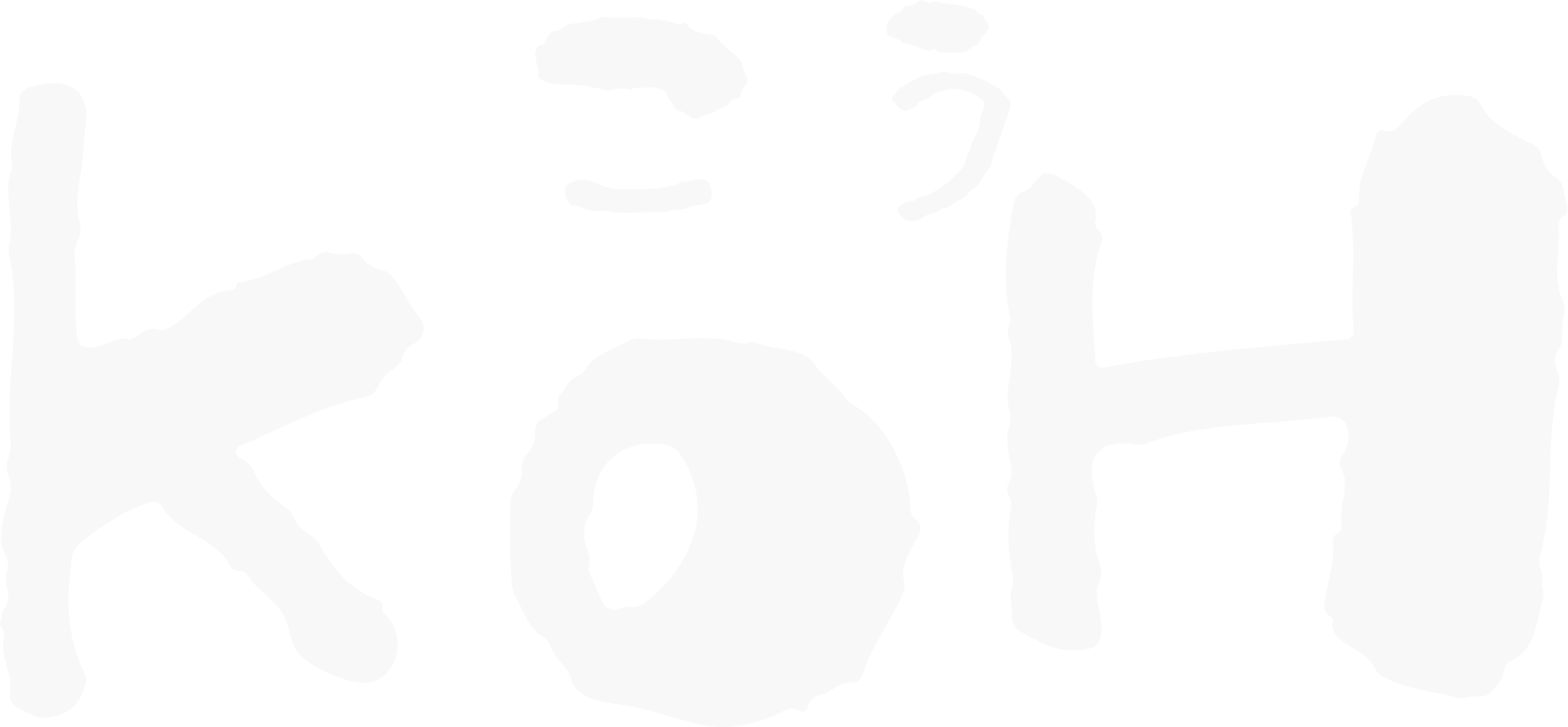【差し金の世界】
差し金(さしがね)は、大工にとって最も身近で、最も奥が深い道具のひとつです。
見た目はただのL字型の金属定規ですが、その使い道は測るだけにとどまりません。
差し金ひとつで「直角を出す」「角度を測る」「勾配を出す」「円を描く」「長さを測る」など、
複雑な作業をこなすことができます。
特に墨付けの際には、柱・梁・床など、複数の部材に正確な角度や位置を出すために必須の道具です。
表と裏で目盛りの間隔が違い、**表は「曲尺(かねじゃく)」、裏は「尺杖(しゃくじょう)」**と呼ばれ、
建築や和裁、木工などで使い分けられてきました。
昔の職人は、差し金1本で一軒の家を建てるとも言われたほど。
シンプルながら、使う人の知識と経験でいかようにも活かせる、まさに「職人の知恵が詰まった道具」なのです。
現代の現場でも、墨付けや加工の際に大工が差し金をさっと取り出して使う姿は、今も変わりません。
1本の金物に込められた、日本の職人文化の奥深さを感じる道具です。