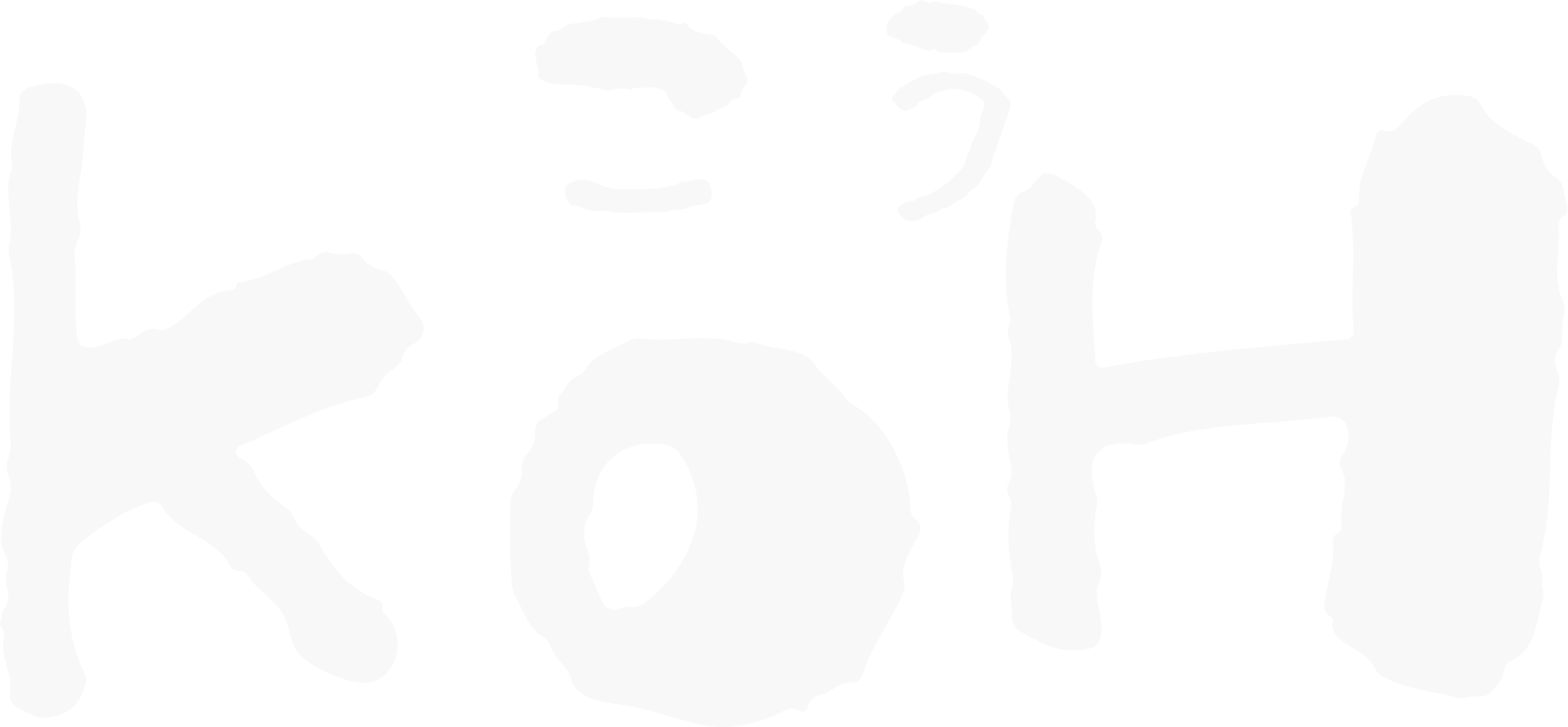【差し金と聖徳太子の関係?】
「差し金(さしがね)」は、大工さんが木材の寸法を測ったり、角度を出したりするために使う道具。
特に直角や45度を正確に測るのに欠かせない、大工道具の代表格です。
そんな差し金に、実は聖徳太子とのつながりがあるという話を聞いたことはありますか?
聖徳太子が建立したとされる法隆寺などの古建築は、釘を使わず木組みで作られています。
その際に柱や梁を組むために必要だったのが、正確な角度や長さを測る定規の原型=差し金。
伝説では、太子の時代にすでに差し金のような道具が使われていたとされ、
「和をもって貴しと為す」という言葉と同様に、日本建築の知恵の象徴として語り継がれてきました。
今では金属製のステンレス差し金が主流ですが、木製や竹製の差し金を使っていた時代もあり、
その歴史の深さに驚かされます。